終末の世界(人と比べない事がテーマの世界)を背景に身体を鍛えて拠点(ホームジム)を変えながら冒険する男の物語。終末前の記憶、筋トレと手に入れた物資(食事)の記録などを綴る。
バルキー小松選手の直感的トレーニング!〜筋トレを楽しんで強くなる方法〜
この記事タイトルにもある通り「筋トレを楽しんで強くなっていく事」ができればめちゃくちゃ強いですよね!
筋トレを継続していくうえで「筋トレを楽しむ方法」は人それぞれ皆んな違ってきますが、
筆者の筋トレを楽しむ方法の1つとしてあげられるのは「”何曜日に○○のトレーニングをする”と決めない事」です。
直感的に筋トレをして自分に縛られない
月曜日は胸の日!とか、胸の日の次は脚の日!とかも特に決まってはおらず、というより決めたくはありません。その日が胸ならばベンチプレス4SETして気に食わなければ次の日も胸の続きをやるとかも全然あります。笑
筋トレメニューにベースはあるもののその週によって明日部位はどこをするのか?を決め気分で決めることが多いです。 気分というのも、主に関節の調子や筋肉痛などと相談してそこから明日のトレーニングのモチベを炙り出し決めています。
こういった「気分で決める筋トレ」は“自分がトレーニングを楽しむため、結果的に筋トレのパフォーマンスを高めるため”に自然と行き着いたものなんです。
よくあるケースとして「今日は脚トレをしなければならない!そうでないと意味がない!」と、自分ルールを作ってしまい日に日に気持ちが重くなていき筋トレを挫折してしまうなんてありがちな話です。
そう”自分”に縛られないため、まずは縛られない筋トレを考えていくのがおすすめ!
こういった比較的「気分で動く要素強めのタイプである事」は自分の中で結構気に入っていた中、トレーニング雑誌ボディビルディング7月号を読んでいると、自分と同じように、いや、それ以上に“直感的にトレーニングを楽しんでいる選手”がピックアップされていたので驚きつつも嬉しくなりましたのでシェアします!
筋トレを楽しんで強くなる方法〜バルキー小松さんを見習え〜
本書を見ていると、直感的に思うがままに筋トレを楽しんでいるのが読んでても分かる人物に注目(スポット)が当てられていた。その人物というのが13年ジャパンオープン優勝者“小松慎吾”選手である。
小松はトレーニングルーティンを持たない。その日になって,「今日はこの部位をトレーニングしよう」と決めているそうだ。また,ある程度のトレーニング種目は決めているが,絶対にこの種目をこの順番で行う,というものも持っていない。いわゆる直感的に今日はこの部位をトレーニングしよう。そしてこの種目を行おう,と決めているのだ。
P7: トレーニングは気の向くまま
小松選手のトレーニングスタイルはまさに今の筆者の上位互換版。「やりたくない種目」をやっていても効かないだろうと言わんばかりに筋トレを純粋に楽しんでる様子がわかります。アドバイス一つ一つに深みがり、頷かされるものがある。
やりたい種目だからやる
気分が乗らなければやらない
非常にシンプルでわかりやすく、尚且つ身体の声をよく聞いている選手だと感じさせられた。
その理由を尋ねると「あまりルーティンとかやる種目とかを前もって決めてしまうと,何かトレーニングが楽しくなくなるじゃないですか」と答える。やはり都会のビルダーには見られないおおらかさが彼にはある。さらに言うならば,彼はトレーニングを休まない。トレーニングを休む日は大会の時か,どうしても疲れているときだそうだが,現在のところ疲れを感じることはないそうだ。
P:7 トレーニングは気の向くまま
やりたいことをやって、尚且休まない。
小松選手の場合「休む」という意識すらなさそうだ。
きっと休まないという意識よりも「いつのまにか、そういえば休んでいないな、などの感覚」に近いのだろう。筋トレが好きだから当たり前に強くなる。楽しんでいるから当たり前に強くなってしまうのだ。
飽きないトレーニングを追求する!
初歩的なことだが、トレーニングにおいて“集中する事”というのは質を高めるために重要なこと。
従って集中力が切れると同時にトレーニングを終えるのも、
楽しいトレーニングを楽しいままに留めておくコツと言える。
また、ダブルスプリット(1日2回に分けてトレーニングを行う方法)を行えば、集中力の回復も狙っていけるだろう。
小松は同じ部位をダブルスプリットで行うし,トリプルスプリットで行うそうだ。その理由は「あまりに長時間同じ部位をトレーニングしていると飽きちゃいますし,集中力も持ちませんから。僕はトレーニングを楽しく行いたいんで,そうしています」
p:8 トレーニングは気の向くまま
これについてはダブルスプリットで回していた時期があるからこそ、深く頷きました。飽きたら辞める、お腹空いてきたから辞めるという感覚で僕も筋トレをしています。「楽しい筋トレ」にこだわるのは継続する為の答えなので、こういう気分トレーニングはハマる人には超絶ハマるのでおすすめ。
下手なこだわりは捨てろ!
肉体改造において、サプリメントは効率的に栄養補給していくためには必須ではあるが、あくまで「効率が良くなるだけのもの」である事を忘れてはならない。ようは固形食に勝るものはないという事。効率を選ぶのか、固形でしっかり摂るのかの差なんだと筆者は考えます。
サプリメントを飲んでいる人の中には、結局は結果を出すためのサプリメントではなく心のサプリメントになってしまっていることも多いのではないだろうか。
休憩中には,プロテインでタンパク質補給。「吸収の良いアミノ酸じゃないの?」と聞くと「プロテインの方が安いですから」だそうだ。
P9: 慎吾の胸トレ
本書を見ているとバルキー小松選手はサプリメントに対して細かいこだわりを持っていない様子。バルキー小松選手にとってサプリメントの吸収が良い悪いは重要ではなく、コスト面を考えている。笑
たくさんトレーニングして基礎的な栄養をぶちこんでおけばいいと言わんばかりである。
いやぁ、ごもっとも!
負荷をかける事だけを追求!
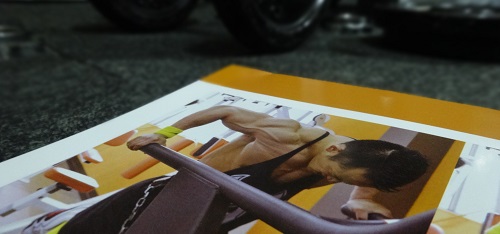
筋トレを継続的に行っていると、徐々に負荷に慣れ始める。
同じような負荷ではプラトー(停滞期)に陥りやすくなる。
これは初心者にも上級者にも立ちはだかる壁。
そこで、フォームに変化を与えることで新鮮な負荷を体におくることも重要となる。
筋トレの方法に少し変化をつけるだけでもプラトーの打破に繋がりやすくなるのだ。
それを考えた時、本書を読んでいるとバルキー小松選手は常に直感的に変化を求めている。結果としてやはりプラトー対策にもなり、筋トレを楽しむ切っ掛けを常に鮮度よく得ているのではないだろうか。
セットの最後の方になると,おもむろに逆を向いてディップスを行いだした。聞いてみたところ「多少刺激が変わるもので」ということで,これといった理由はないみたいだ。
P:9 慎吾の胸トレ~ディップス~
すべてのセットに置いて,ディセンディングセットで追い込む。おっと,なんだかセットの途中でスミスマシンへと移り,さらに追い込んでいるぞ。その理由は,予想通り「多少刺激が違うもので」という短絡的なもの。
P:12 慎吾の胸トレ~インクラインバーベルプレス~
細かい変化をも自ら歓迎し、負荷をかける事だけを追求する。
そうして筋トレを楽しんでいるからこそ、バルキー小松選手の筋肉は優勝レベルまでに発達したのだろう。
常に楽しんでいるその姿勢は全力でありながらも、それが自然である事が本当に凄い。
それでは今回はここまで。
本日も良き一日を。
コメント